こんにちは、すぺ子ママです。
我が家の娘は自閉スペクトラム症(ASD)で、口の中の感覚が過敏です。
味だけではなく食感や見た目にもとっても敏感で、もうすぐ5歳になりますが毎日苦労しています。
ですが母親である私は料理が大の苦手…
今回はそんな娘に少しでも食べてもらえるよう、私なりに試してみたことや工夫していることをご紹介します。
子どもの感覚過敏や偏食で悩んでいるご家庭の参考になれば幸いです。
娘の発達障害の程度
3歳10カ月の時に、医師より自閉スペクトラム症(ASD)の診断を受けています。
知的部分については境界知能です。
離乳食の時期はわりとなんでも食べてくれる『食べることが好きな子』だと思っていました。
1歳を過ぎて幼児食に切り替わると、だんだんと偏食と思えるようなことが増えてきました。
- 初めて見るものは絶対に食べない
- 混ざっているものは食べない、分ければ食べるものもある(焼きそばに入っている野菜など)
- きのこ類は絶対に食べない
- シャキシャキの食感は好き、ふにゃふにゃは嫌い
- 色んな食感のする食べ物は食べない(出してしまう)
- 昨日は食べたのに今日は食べない『気分』によるものも多数
- 果物は好き(皮つきで食べるサクランボやブドウはNG)

むりむりむりむりむりむり
料理のできない私にとって、娘のリクエストを叶えられる気がしない。
それでも母親としてやるしかない!と奮闘した記録を残しておきます。
残念ながら娘には効果のなかったもの2つ
かわいい食器にする
よく目にするアドバイスのひとつで、かわいい食器にするというもの。
LECさんのサイトにあるようなキャラクター食器のイメージです。
娘はアンパンマンやトーマスなどのキャラクターが大好きなので、いけるかな?と思って試しましたが効果なし。
初めは「わー!アンパンマンだ!」みたな反応をしてくれるのですが、食べるかどうかは全く別の話のようでした。
残念!
料理の見た目を可愛くする

こちらも、料理が苦手な中で色々工夫してみました。
- ハートや星の形の型抜きを使う
- キャラクターの印刷されているソーセージやかまぼこ等を試してみる
- ケチャップで絵を描く
- アンパンマンポテト(冷凍)を試してみる
こちらも形やキャラクターには興味を持つものの、逆に『得体のしれないもの』認定されてしまったようで口に入れることはありませんでした。涙。
効果のあったもの6つ
食べる前にそれが何であるか説明する(4歳~)

『初めて見るもの』や『得体のしれないもの』には絶対に手を出さない娘。
言葉が理解できる時期になったらきちんと『それが何で構成されているのか』を説明しました。

これはハンバーグだよ~
ハンバーグには牛さんのお肉と、豚さんのお肉と、玉ねぎと、卵が入ってるんだよ~

こっちはお味噌汁だよ~
今日のお味噌汁には、にんじんと、大根と、お豆腐が入ってるよ~
そんな具合に説明すると『苦手なもの』や『知らないもの』は入っていないと理解してくれるようで、食べてくれることが増えました!
保育園で給食のいただきますの前に、今日の献立をみんなで読み上げているという習慣をヒントにして取り入れてみました。
食べる前に量を相談する(4歳~)

完食して食器がピカピカにできた!という体験はとても自信に繋がるようです。
その『成功体験』を重ねるということと、療育でよく耳にする『スモールステップ』の合わせ技で、食べる前に本人と量を調整しています。
まずは標準の量で盛り付けて食卓に並べます。
それを見せたうえで「減らすものがある?」と聞くようにしています。

今日のご飯はサラダとお味噌汁と唐揚げとご飯です。
減らすものあるかな?

サラダ減らしてー
にんじんは好きだから減らさないでね!
4歳半を過ぎたあたりからこんなやり取りができるようになりグッと楽になりました。
娘自身も、自分が決めた量を完食できるととても嬉しそうです。
(おかわりをする日もあります!)
混ざりものは分けるor隠す
娘は混ざっているものは基本NGです。
特に食感の違うものが混ざるのが嫌なようで、別々に分けて出すと食べてくれることもあります。
例えば焼きそばの場合
- 麺
- もやし
- ウインナー
- キャベツ
- にんじん
をそれぞれ皿を分けて出すと、好きなものから順番に食べます。
最後に残るのがだいたい葉物野菜です。
我が家では完食は目標にせず、次にあげる『いっこだけルール』が守れれば全部食べ切らなくてもOKにしています。
「苦手なものはいっこだけ」の合言葉
娘自身も完食に向けて頑張りたい気持ちはとてもあります。
それでも苦手なものはやっぱり苦手。
キノコ類は完全にNGですが、それ以外のものは「いっこだけ」なら頑張れるそう。(日によりますが)
なので試しに「苦手なものはいっこだけ」の合言葉を作ってみたところ効果バツグン!
今では

苦手なものは~?

いっこだけ!!!
という具合に、ふたりの合言葉になっていて、自分で「いっこだけ」という事で娘自身も頑張れるみたいです!
デザートでやる気アップ(2歳頃~)
保育園の給食で「デザートは一番最後に食べる」ということを教わってきました。
そして果物が大好きな娘。
例えばみかんを食卓に置き、一口食べるとちょっとだけ近づいてくる。
そんな演出をしてみたらみかんが近づいてくるのが面白いのと、早く食べたいのとで目の前のおかずも頑張ってくれました。
※気分によってダメな日もあります
絵本や図鑑で《知っている》食べ物を増やす(2歳頃~)
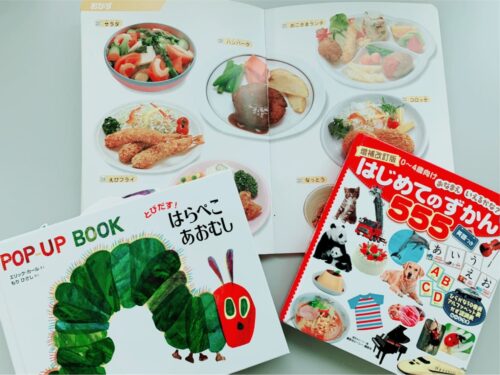
娘の場合、前の項目でもあったように『得体のしれないもの』がとにかく苦手。
なので「知ってる!」を増やすことに専念しました。
本当は栽培などするとより身近に感じられるのですが、我が家ではできないので絵本や図鑑に助けてもらいました。
- はじめての図鑑シリーズ
→野菜などの素材以外にも料理として出来上がったものが載っています - はらぺこあおむし
→あおむしが食べてた〇〇だ!という親近感が良かったようです - おべんとうバス
→たまたま1歳の時に保育園のお遊戯会でやった演目でお弁当の具を覚えました - グリーンマントのピーマンマン
→ピーマンってカッコイイ!と思ってくれたようで一口だけなら食べられるようになりました
歌で親近感を覚える(2歳頃~)
これも絵本や図鑑と同様に親近感を覚えて「知ってる!」を増やす作戦の一つです。
- はらぺこあおむし
→絵本と同じ理由です - おべんとうばこのうた
→出てくる食材がなかなかシブイのですが、唯一「穴の開いたレンコンさん」に惹かれたようでレンコンはわりと進んで食べてくれます
朝食は定番のワンパターン(1歳頃~)

自閉スペクトラム症(ASD)の子には『同じことを繰り返すと安心する』という特性がある子います。
娘の場合もまさにこれ。
この特性を利用して、朝食だけは毎日同じものを用意するようにしています。
(栄養が偏り過ぎないよう、保育園の給食と夕飯で不足する部分を補うイメージです)
- バナナ(半分~1本)
- バターロール(1こ)
バターロールはバターorいちごジャムの選択制にして、その日に娘が選んでいます。(だいたい同じ方が1週間くらい続きます)
手抜きのようにも見えますが、別の物を出してもバナナとバターロールを要求されるのが現実。
こだわりでもありますね。
時間の無い朝、お互いにいい気分で出発できるよう、あえてこのスタイルを続けています。
番外編 粉薬の飲ませ方
娘は1歳の頃から副鼻腔炎で、毎日朝晩と粉薬を飲んでいます。
初めのうちはミルクに混ぜて問題なく飲めていましたが、卒乳後の飲ませ方は試行錯誤の連続でした。
少量ではあるものの、苦いと名高い抗生物質を毎日2回飲ませなくてはならない。
有名な「お薬飲めたね(ゼリー)」はNG、チョコレートでのコーティングもNG。
口の中が敏感なので牛乳やお茶に混ぜても味おかしいとすぐにバレていまい…
最終的にたどり着いたのが、ホイップクリーム(生クリーム)でのコーティングでした!
多少味は変わるのですが娘自身ケーキなどのクリームが大好きなので、好きが勝ったようです!
既にホイップされた商品がスーパーで買える良い時代です!
脂質など気にはなりますが、ティースプーン一杯を1日2回。そこは目を瞑ることにしました。
終わりに
感覚過敏の偏食っ子に付き合うのは、本当に大変です。世のパパママたちも苦労されていると思います。
赤ちゃんの時、栄養士さんに言われたことは「とにかく食事の時間を嫌いにさせない」ということ。
せっかく栄養を考えて作っても拒否される、メンタルゴリゴリ削られますよね。
元々料理が苦手な私は割り切りました、料理は頑張らない!(笑)
ここまで読んでくださった方はお気づきかもしれませんが、実は私がやっていることは「演出」なんです。
- 『得体のしれないもの』を減らすためにそれが何で出来ているかを説明する
- 食べる前に量を相談する
- 合言葉を作って一口だけ頑張ってみる
- 絵本や図鑑で『知っている』ものを増やす
- 歌で親近感を持たせる
- 朝食はワンパターンでお互い無理をしない
子どもが楽しく食事に取り組めるように「演出」することで、料理が出来なくてもなんとかなっています。
手を抜けるところは抜きましょう!それでも子どもは大きくなります。
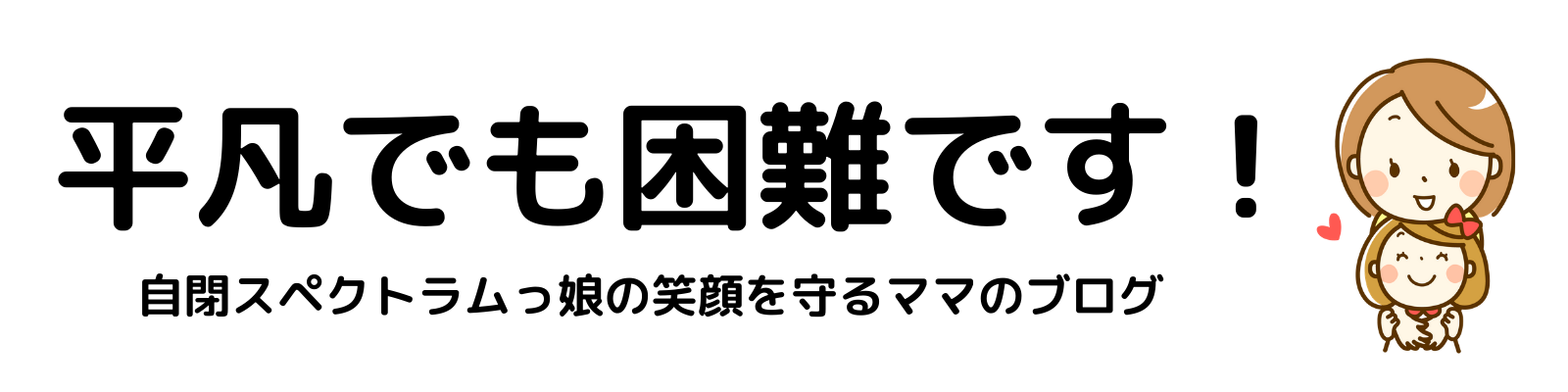
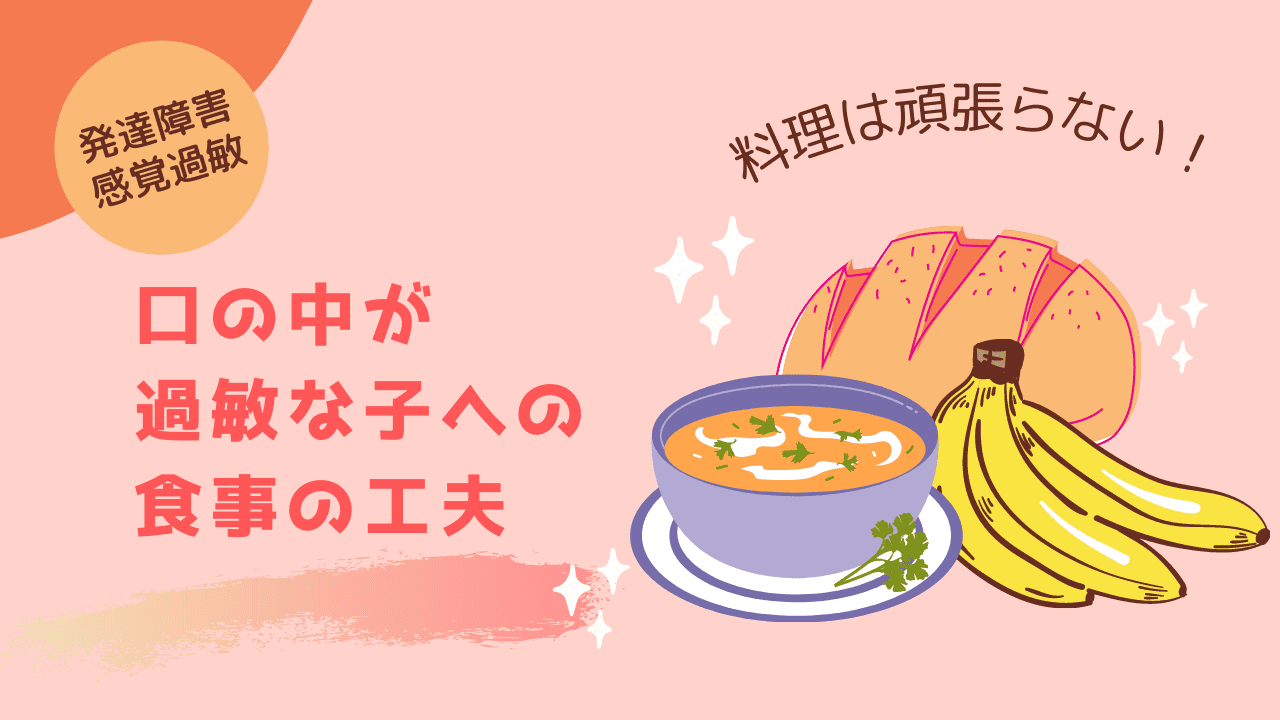
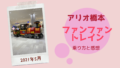

コメント